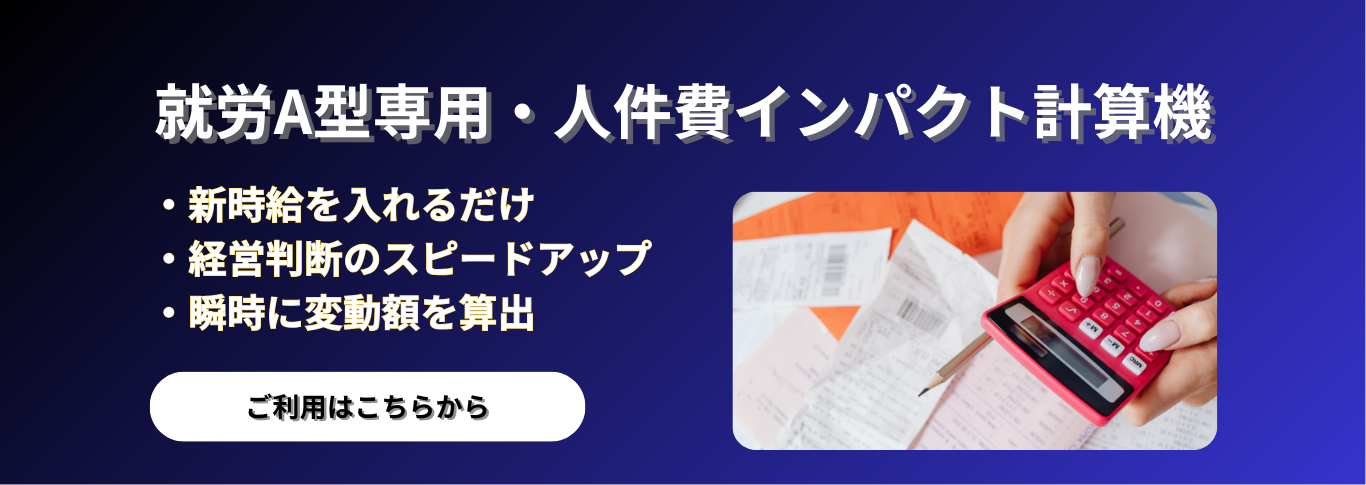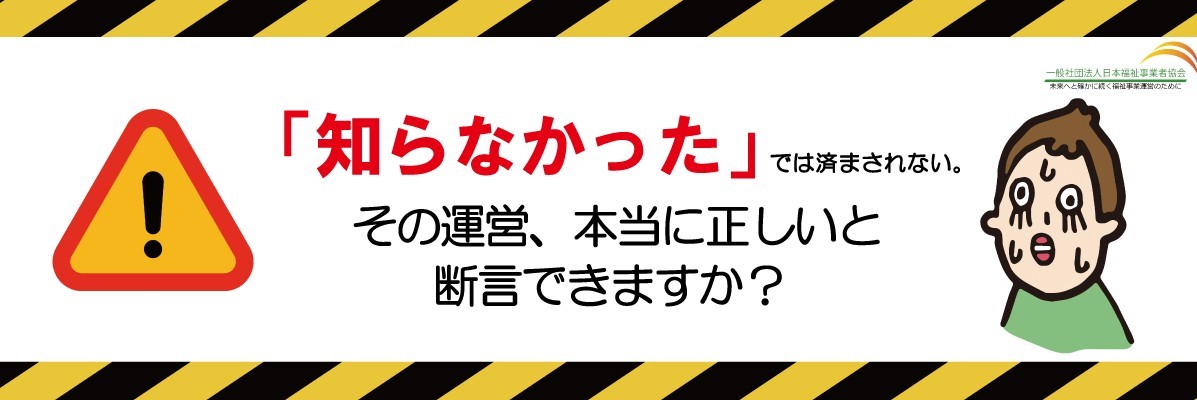就労継続支援A型の助成金と補助金は?運営実態と一緒に解説2025.05.15

● A型事業所の開業で使える支援金はあるの?
● 助成金と補助金は何が違うの?
● 運営を成功させるためには助成金・補助金をどのように活用すればいい?
国が支援する就労継続支援A型の事業では、さまざまな助成金や補助金が用意されており、それぞれの違いや要件を理解できずに悩む方が多いです。
収益化を成功させるためにも、助成金や補助金の仕組みについて理解して、どれを利用できるのか把握しましょう。
- 就労継続支援A型の助成金と補助金の概要
- 収益モデルと運営費用の実態
- 就労継続支援A型の支援金の適用要件
就労継続支援A型で使える助成金・補助金の概要

国や自治体は就労継続支援A型に関する支援を受ける際に、「そもそもどのようなものがあるのだろう」「誰でも受給できるのだろうか」と疑問に思う方は多いです。
助成金と補助金は、どちらも国や自治体が提供している支援金といった点では共通していますが、申請方法や受給条件が異なります。
ここでは、就労継続支援A型向けに提供されている助成金・補助金の違いをお伝えしたうえで、それぞれの特徴について解説します。
助成金と補助金の違い
助成金と補助金は、国や地域の自治体が提供している支援金である点では共通していますが、それぞれ特徴や公募期間などが異なります。
| 助成金 | 補助金 | |
| 特徴 | ●雇用保険に加入している従業員に対して、一定要件を満たせば受給できる可能性が高い。国の予算額の中で実施。 | ●会社の設備投資や生産性向上のための経費について、所定の%で補助金がでる ●採択件数や上限金額が決められているケースが多い |
| 受給の難易度 | 低い | 高い |
| 公募期間 | 長い | 短い |
| 金額 | 少額な場合が多い | 少額から数千万円規模まである |
| 支払いのタイミング | 申請後、比較的早く払われる | 基本的には後払い |
| 実施機関 | 厚生労働省 | 地方自治体 |
このように助成金と補助金では、いくつかの違いがあります。
しかし中には、助成金といいつつも、厳しい審査や採択件数の制限があるなどの補助金に近しい特徴を持つ支援制度も含まれているので、注意が必要です。
誤解しないためにも、具体的な適用要件や申請方法などをよくみたうえで、活用するべきか判断しましょう。
就労継続支援A型で使える助成金
就労継続支援A型で使える助成金とは、厚生労働省と各自治体が管轄している支援制度の一種です。
おもに、雇用の新規確保と安定のために用意されています。
一定要件を満たしていて適切な手順で申請をおこなえば、支給してもらえるため、補助金と比べると受給の難易度が低いです。
また、公募期間が数か月〜1年間以上ある場合が多く、計画的に準備をすれば支援を受けられる可能性が高いですが、常にアンテナを張って、受給チャンスを逃さないようにしましょう。
公募期間は長く設定されていても一定要件など、定期的に内容が変更されているので、申請前には最新情報を確認しましょう。
就労継続支援A型で使える補助金
就労継続支援A型で使える補助金とは、経済産業省と各自治体が管轄している支援制度の一種です。
おもに、事業の拡大や技術や設備投資のために用意されています。
多くの場合は、支援できる採択件数や上限金額が決められているので、申請数が殺到すれば審査を通じて受給者が決められます。
審査基準は、あらかじめ提示された一定要件を満たしているのが前提であり、さらにほかの申請者たちよりも魅力をアピールしなければなりません。
数倍から数十倍の倍率になるケースも珍しくなく、計画的な申請をおこなっても審査に落ちる場合が多く、難易度が高いです。
また、公募期間が数週間〜1か月程度の短期間に設定されている場合が多いので、常にアンテナを張って、受給チャンスを逃さないようにしましょう。
就労継続支援A型事業所の収益モデルと運営費用の実態

就労継続支援の事業所はA型とB型に分かれており、さまざまな障がいを抱えた方たちが就労やスキル習得の機会を得ています。
助成金や補助金を活用して事業所の開設や運営を検討しているのであれば、事業所の仕組みや収益構成を把握する点から始めるのが重要です。
ここでは、就労継続支援A型と就労継続支援B型の違いをお伝えしたうえで、収益モデルや運営費用の実態について解説します。
就労継続支援A型とB型の違い
就労継続支援A型とB型は、どちらも障がいを抱えた労働者が在籍する事業所である点では共通していますが、いくつかの違いがあります。
| 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
| 特徴 | 一般企業での就職が難しい場合に事業所内で雇用契約を結んで働く | 雇用形態を結ばない代わりに自分のペースで働けたり就労に必要なスキルを習得できたりする |
| 雇用契約 | あり | なし |
| 賃金 | 最低賃金以上が保障される | 工賃(生産活動に対する対価が支払われる) |
| 助成金と補助金 | 手厚く用意されている | A型よりは少ない |
| 作業内容 | ●データ入力 ●ホールスタッフ ●パッキング ●作業代行 など |
●手工芸 ●部品加工 ●農作業 ●封入作業 など |
令和3年度の調査では、A型一人あたりの月間平均給料は81,645円(時給換算:926円)に対して、B型一人あたりの月間平均給料は16,507円(時給換算:233円)でした。
労働時間や業務内容が異なりますが、A型では最低賃金以上の支払いが義務化されているので、B型よりも運営費用が高くなります。
B型は雇用契約がなく、雇用保険の加入もないため、助成金を原則、受給できません。
A型は助成金制度も活用して、安定した経営を行う必要があります。
就労継続支援A型の収益モデル
就労継続支援A型の収益源は、以下の3点です。
● 生産活動売上
● 給付金
● 助成金や補助金
内職や軽作業など利用者の業務内容は異なりますが業務によって発生した売上や、国から支給される給付金(基本報酬)がおもな収益源となります。
ここでいう給付金とは、利用者数や生産活動の収益など複数の項目から総合的に評価された結果によって決まります。
厚生労働省の調査では、生産活動の収益が利用者の賃金を下回っている事業所が56%以上との結果がでており、健全な収益モデルが構築できていないケースが多いです。
こういった事態になっている背景として、就労継続支援A型の利用者には最低賃金以上の支払いが義務付けられており、負担が大きい点が挙げられます。
そこで、助成金や補助金をうまく活用すると、雇用の安定や収益の増加が見込めます。
とくに助成金は、一定要件を満たせば、支給される制度ですので、情報を漏らさずに得て、申請し活用することが重要です。
補助金に関しては、審査の難易度が高いものの、採択されると大きな金額を得られることも多く、計画的に準備をして申請してみてもよいでしょう。
就労継続支援A型の運営費用の実態
就労継続支援A型の運営費用は、以下のとおりです。
● 初期費用(法人設立費、物件取得費、雑費など)
● 人件費(障がい者への給与、生活支援員への給与)
● 運転費用(事業所の家賃、光熱費、設備の購入、修理費など)
就労継続支援A型の運営費用で最も多くの割合を占めているのが、利用者と生活支援員の給与です。
工賃の支払いとなるB型の利用者とは異なり、A型の利用者とは雇用契約を締結しているので、最低賃金以上の給与の支払いが求められます。
また、利用者の社会保険料や労働保険料の支払いも事業所が負担する点も、あらかじめ理解しておきましょう。
また、利用者たちに業務の指示をしたり体調を確認したりする生活支援員の常駐が必要となるので、その方たちへの給与も発生します。
そのほかにも事業所の開設で必要な初期費用(イニシャルコスト)や維持するための運転費用(ランニングコスト)が必要です。
立ち上げて初月から安定した収益がでるとは限らないので、助成金や補助金を頼りにしつつ、より多くの自己資金を確保できるかどうかが事業所存続の鍵となります。
就労継続支援A型事業所が活用できる助成金と詳細

就労継続支援A型は、B型と比べて助成金が充実していて申請の難易度も低いですが、どういった種類があるのかわからずに困っている方は多いでしょう。
ここでは、就労継続支援A型事業所が活用できる助成金について解説します。
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、高齢者や障がい者など一般企業での就労がむずかしいとされる方を雇用した際に支給される助成金です。
A型事業所が対象になるのは、以下の2種類です。
| 支給額 | 助成対象期間 | |
| 特定就職困難者コース | 短時間労働:80万円(30万円) 短時間労働以外:120万円(50万円) |
短時間労働:2年(1年) 短時間労働以外:2年(1年) |
| 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース | 短時間労働(中小企業):80万円 短時間労働(中小企業以外):30万円 短時間労働以外(中小企業):120万円 短時間労働以外(中小企業以外):50万円 |
短時間労働(中小企業):2年間 短時間労働(中小企業以外):1年間 短時間労働以外(中小企業):2年間 短時間労働以外(中小企業以外):1年間 |
ここでいう短時間労働とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の利用者を指しています。
特定就職困難者コースの場合、一般企業への就職を目指している利用者が在籍していれば、3年間で最大240万円支給される可能性があります。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、障がい者の雇用の促進と安定を目的としており、有期雇用から正規雇用・無期雇用に転換された際に支給される助成金です。
支給額や措置内容、措置内容は、以下のとおりです。
| 支給対象者 | 措置内容 | 支給額 | 支給対象期間 |
| ・重度身体障害者 ・重度知的障害者 ・精神障害者 |
有期雇用から正規雇用への転換 | 120万円(90万円) | 1年(1年) |
| 有期雇用から無期雇用への転換 | 60万円(45万円) | ||
| 無期雇用から正規雇用への転換 | 60万円(45万円) | ||
| ・重度以外の身体障害者 ・重度以外の知的障害者 ・発達障害者 ・難病患者 ・高次脳機能障害と診断された者 |
有期雇用から正規雇用への転換 | 90万円(67.5万円) | |
| 有期雇用から無期雇用への転換 | 45万円(33万円) | ||
| 無期雇用から正規雇用への転換 | 45万円(33万円) |
()なしは中小企業、()ありは中小企業以外を指しています。
利用者1人あたりに支払われる金額ですが、支援金額が利用者の賃金を上回る場合は、賃金総額が上限となるので注意が必要です。
職場適応訓練費
職場適応訓練費は、事業所で利用者が生産活動をおこなうために必要な作業訓練をする際に支給される助成金です。
作業訓練に必要な設備と指導員が揃っていて、労働災害補償保険・雇用保険・健康保険などの各種保険に加入しているなどの条件を満たしている必要があります。
一定要件を満たせば、利用者1人あたり月額24,000円(重度の障がいを持つ利用者は1人あたり25,000円)、短期間の訓練では日額960円(重度の障がいを持つ利用者は1人あたり1,000円)支給されます。
作業訓練を受けた事業所で雇用してもらう目的もあるので、スキル習得と雇用の安定を目指す制度です。
障害者介助等助成金
障害者介助等助成金は、一定基準を超える障がい者を雇用した際に独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から支給される助成金です。
常時雇用されている労働者が100人を超えている企業が対象となっており、そのうち障がい者の数に応じて1人あたり月額29,000円を支給します。
ここでいう労働者とは、以下のとおりです。
● 一般労働者:毎月の所定労働時間120時間以上
● 短時間労働者:対象期間に該当する月の所定労働時間が80時間以上120時間未満
● 特定短時間労働者:対象期間に該当する月の所定労働時間40時間以上80時間未満
特定短時間労働者は、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者のいずれかに当てはまる人が対象です。
なお、法人の代表者や役員、事業主と同居している親族や学生は対象外となるので、3つのいずれかの条件を満たしている労働者が100人いるかどうかが重要です。
特例給付金
特例給付金は、短時間労働できる障がい者を雇用した際に支給される助成金です。
令和3年に発足された制度ですが、令和6年4月1日に廃止されているので、それ以降の新規雇用者に対する支給はありません。
なお、令和6年3月31日までに雇用されている場合、令和7年3月31日までの1年間は経過措置が適用されるので、引き続き支給されます。
| 事業主区分 | 支給対象の雇用障がい者 | 支給額 | 支給上限人数 |
| 100人以上 | 週10時間以上20時間未満 | 利用者1人あたり月額7,000円(調整金27,000円) | 週20時間以上の雇用障がい者数(月ごと) |
| 100人以下 | 利用者1人あたり月額5,000円(調整金21,000円) |
支給総額は、雇用している利用者の数に応じて変動します。
一般企業で長時間の労働は困難であるものの、短時間であれば働ける労働者の職業的自立を目的としています。
まとめ
就労継続支援A型は、利用者に対して最低賃金以上の給与を支払う義務があるため、B型に比べ人件費の負担が大きいですが、その代わりに雇用に基づいた助成金を取得することが可能です。
この利点を最大限に活かし、安定した経営を行うことで、一般企業での就労が難しい障がいを抱える人たちの雇用によるスキル習得と自立を支える機会を提供することが求められています。
それに加えて補助金等も活用するなど、情報を適切に取得し、経営面でできることをしっかりとやっていくことが就労継続支援A型の運営においては非常に重要と言えるでしょう。
当協会では、福祉事業のオーナー様向けに各種勉強会やお役立ち情報を発信しています。
協会員様になられた方には当協会が主催する「オンライン講座」に無料で参加&視聴できます。