就労継続支援A型の現状と今後は?課題と改善策や成功事例を解説2025.04.07
● 就労支援制度A型の事業所の閉鎖や利用者の解雇が増えているって本当?
● 経営者、企業として事業所を存続させるために何をするべき?
● 具体的な成功事例ってあるの?
就労継続支援A型は、障がい者の雇用機会を設ける福祉制度の一種ですが、事業所の閉鎖や利用者の解雇が相次いでいます。
現在、就労継続支援A型をおこなっている事業所やこれから利用を検討している事業所は、どういった点に注力すれば良いのでしょうか。
こちらの記事では、就労継続支援A型の現状をお伝えしたうえで、複数の視点から課題や改善策、成功事例について解説します。
- 就労継続支援A型の現状
- 経営者、企業視点で考える課題と改善策
- 利用者の声から見るサービス向上の具体策
- 2024年の改定に伴う対処法
- 経営難による閉鎖リスクを回避する方法
就労継続支援A型の閉鎖と解雇の現状

就労継続支援A型は、障がいを持つ人を対象に雇用機会を設けるために発足された支援制度です。
しかし、厚生労働省が発表した「就労継続支援A型の状況について」の調査によると、2024年3月から2024年7月の5カ月間で4,279名が解雇されたとの結果が報告されています。
就労継続支援A型事業所解雇数の推移が、以下のとおりです。
| 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解雇数 | 698名 | 887名 | 1,241名 | 766名 | 687名 | 4,279名 |
なお、 解雇された4,279名の 再就職状況は、以下のとおりです。
| 再就職決定者 | 936名(うちA型事業所への再就職者は696名) |
|---|---|
| B型事業への移行(予定)者 | 2,073名 |
| 求職中 | 949名 |
| そのほか | 321名 |
解雇された就労継続支援A型利用者のうち、約7割は再就職もしくはB型事業への移行(予定)が決まっていますが、約3割は求職中です。
就労継続支援A型からB型に移行すると解雇という扱いになり、収入が著しく減少します。
よって、現在は約3,000人の解雇者が新しい仕事を探している状態であり、就労継続支援A型利用者の雇用の不安定さが際立つ結果となっています。
就労継続支援A型事業所の閉鎖や解雇が増えている要因
就労継続支援A型事業所の閉鎖や解雇が増えている最も大きな要因は、令和6年の報酬改定によって、利用者が自分の賃金を上回る事業収益を稼ぐことに評価が集中した点にあります。
この改定により、事業所は最低賃金と社会保険料を上回る事業収入を毎時確保しなければならなくなりました。
また、賃金や社会保険料の負担が増えたことで、事業所が求められる事業収益も高くなっています。
しかし、就労継続支援A型事業所には精神的に不安定な方や体調不良でお休みがちの方など、さまざまな障害や特性を持った利用者が通ってるのが現状です。
それらの方が一律に最低賃金と社会保険料を上回る事業収入を求められることが、事業の運営を著しく困難にしています。
このため、多くの就労継続支援A型事業所が閉鎖に追い込まれ、多くの利用者が職を失う状況が続いています。
今後、事業所が事業収入以外の点でも評価されるような仕組みが必要であり、それがなければ事業所の閉鎖や解雇が増える状況は続くと考えられるでしょう。
経営者と企業視点で考える就労継続支援A型の運営方針・課題と改善策

就労継続支援A型事業所の閉鎖や解雇が増えている現状を踏まえて、どのような課題が残っているのでしょうか。
ここでは、就労継続支援A型事業所を存続させるための運営方針を課題と改善策と一緒に解説します。
収益性と社会貢献の整合性
多くの就労継続支援A型事業所では、内職を中心とした軽作業が主流となっています。
このような作業内容では、どうしても最低賃金を上回る収益を確保することが難しくなります。
実際、軽作業では単価が低いため、利用者の賃金を引き上げることはほぼ不可能と言えるでしょう。
この状況を打破するためには、より高度で単価の高い多様な仕事を提供できる環境整備が必要です。
そのためには、新たなビジネスモデルの導入や、職員によるスキルアップの支援体制を構築しなければなりません。
たとえば、利用者が専門的なスキルを身につけるための研修プログラムや、業務の多様化を図るための新しい事業の立ち上げなどが考えられます。
これにより、就労継続支援A型事業所自体の収益性を高めると同時に、利用者の自立を促すことも可能となるでしょう。
また、障がい者施設だから安く仕事を請け負わせるという社会的な通念を変えることも重要です。
この偏見を解消し、障がい者の方々が能力に応じた対価を得られるような社会の実現が求められています。
利用者が自分のスキルや努力に見合った賃金を得られることで、彼らのモチベーションも高まり、結果的に社会全体への貢献につながります。
そのためには、企業や社会全体が障がい者の働き方に対する理解を深め、適切な報酬を支払うことが重要です。
このようにして収益性と社会貢献が調和することで、就労継続支援A型事業所の持続可能な運営が可能となり、より多くの障がい者の方々に安定した雇用を提供できる社会が実現するでしょう。
地域と連携した持続可能な経営
就労継続支援A型事業所は、施設内の作業だけでなく、地域社会で求められる仕事にも積極的に参入することが重要です。
これにより、専門性の高い高単価の仕事を得ることが可能になり、事業所の収益が向上します。
地元での信頼構築は、成功するために欠かせない要素といえるでしょう。
地域社会との連携を深めるためには、まず地域のニーズを正確に把握することが大切です。地元の特性や特産品、企業のニーズを調査し、自事業所の貢献方法を明確にすることで、地域からの理解を得やすくなります。
次に、地域のイベントや活動への参加も効果的で、ボランティアとして参加することで地域の人々との関係を築けます。
地域企業とのパートナーシップも重要であり、協力関係を結ぶことで新しい雇用機会を生み出し、地域全体の福祉を向上させることができます。
最後に、地域住民とのコミュニケーションを重視し、定期的な情報発信や交流会などを通じて事業の取り組みを紹介していきましょう。
地域と地域住民との距離を縮め、就労継続支援A型事業所をポジティブなイメージにすることが期待されます。
利用者の声が示す就労継続支援A型サービス向上への具体策と成功事例
実際に就労継続支援A型を利用して良かったと感じている人たちは、どういったところに魅力を感じているのでしょうか。
ここでは、就労継続支援A型サービスの向上に向けた具体策と成功事例について解説します。
地元密着型の職業訓練
地域にあるほかの会社と提携を組んで、利用者に向けた職業訓練やアシスタントをおこない、実践的なスキルを身につけさせて雇用機会につなげます。
具体的には、地域の特産品を生かした商品開発、販売などに利用者が参加することで、地域住民との接点が増えます。
利用者の特定スキルの向上はもちろん、地域内の経済活性化や雇用機会の獲得、地域全体の障がい者雇用理解への深まりが期待できるでしょう。
地域密着型の商品開発や販売事例
地域の特産品を用いた商品開発や販売業務を積極的に進めることで、地域住民との直接的なつながりを増やしました。
この取り組みは、単に商品を売るだけではなく、地域の文化や特色を理解し、地元の人々との交流を深めることを目指しています。
その結果、利用者は実践的なスキルを身につける機会が増え、自信を持って地域に貢献できるようになるでしょう。
また、このような取り組みは地域経済の活性化にも寄与しています。
特産品を活用した商品が地域内外で需要を持つことで、地域の魅力が再認識され、観光や新たなビジネスの機会を生み出しています。
さらに、企業側も地域密着型の取り組みにより、新たな人材を確保しやすくなっており、長期的には雇用の拡大にもつながっています。
結果として、地域全体が活性化し、それぞれにメリットがもたらされるような関係が築かれているのです。
社内の意識改革事例
スタッフの意識改革は、事業の成功に向けた重要な要素です。
定期的に実施されるワークショップや勉強会を通じて、スタッフが自主的に学び合う文化を育んでいる事例があります。
この取り組みでは、各スタッフが自身の経験や知識を活かし、問題解決のためのアイデアを共有することで、全体のスキル向上が可能です。
厳しい環境においても柔軟に対応しながらイノベーションを生み出す可能性を示しています。
他の事業所もこのような取り組みを取り入れることにより、経営の安定性を高め、利用者に対して質の高い支援を提供できるでしょう。
また、新しい考え方や手法を導入し、持続可能な発展を目指す姿勢が求められています。
最終的には、利用者が感じる就労継続支援A型事業所の現実は多様であり、それぞれのニーズに応じた支援が必要です。
利用者の声を真摯に受け止め、より良い環境を整備していくことで、共生社会への道が開かれることが期待できます。
2024年問題と就労継続支援A型事業所の運営戦略と指導
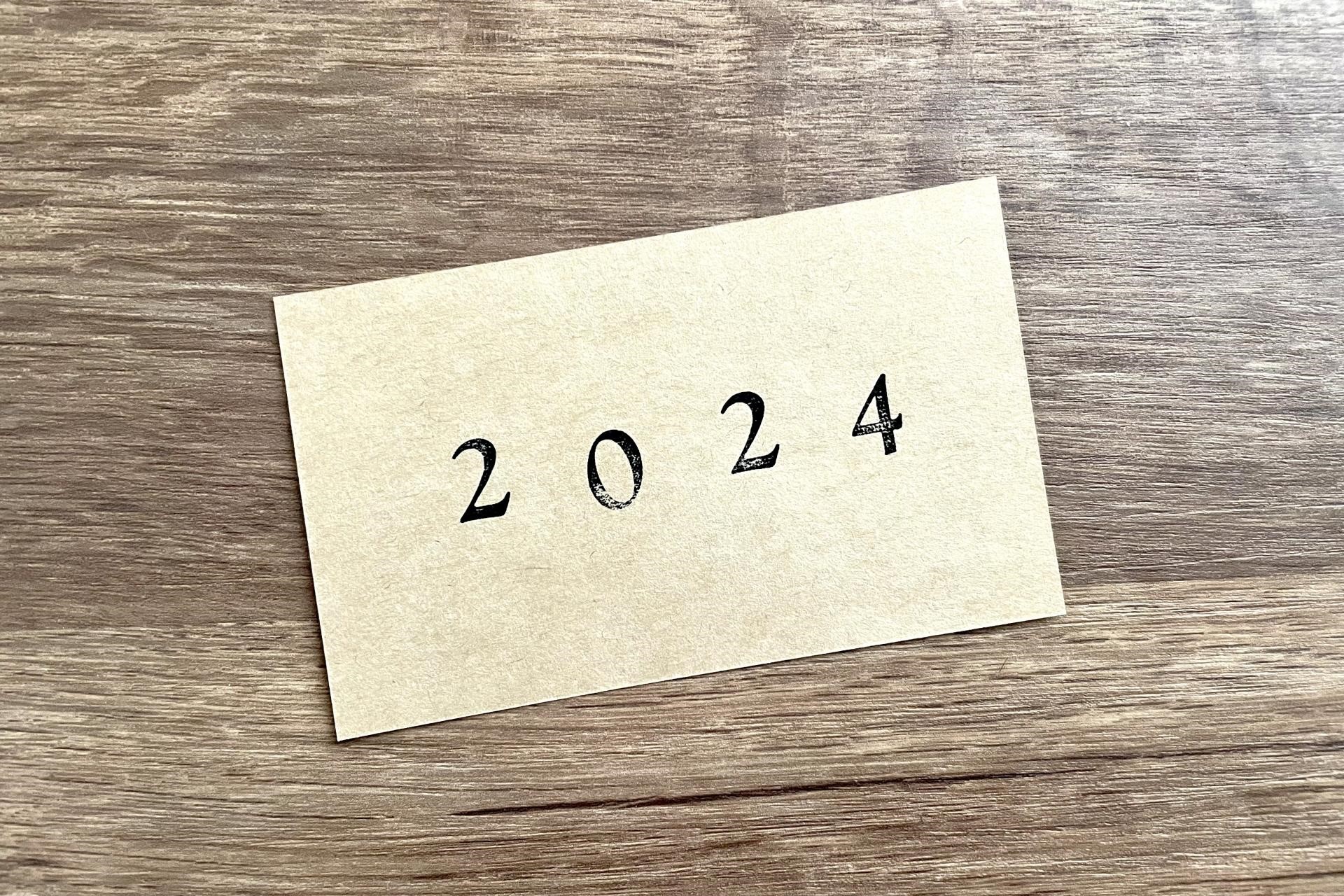
2024年には、就労継続支援A型の報酬改定がおこなわれました。
この改定により、生産活動が赤字だとマイナス点がつき、大幅な基本報酬の減収が発生することが大きなポイントです。
報酬単価を算定するための評価指数の変更点は、以下のとおりです。
● 「労働時間」のスコアが増加した
● 「生産活動」の判定スコアが増加した
● 「多様な働き方」の判定スコアが減少した
● 「支援力向上」の判定スコアが減少した
● 「経営改善計画」の評価項目が増えた
● 「利用者の知識及び能力向上」の評価項目が増えた
報酬単価を高くするには、従来の運営方法を見直し、戦略を再構築する必要があります。
労働時間の確保
リモートワークやフレキシブルな勤務形態を導入することにより、障害を持つ方々が自分のライフスタイルに適した働き方を選べるようになります。
たとえば、リモートワークの導入は、通所に伴うストレスや移動の負担を軽減するだけでなく、家庭の事情に応じた柔軟な働き方を可能にします。
また、事業所がオンラインでのサポート体制を整えることによって、利用者に必要なスキルを身につけるための機会を提供しやすくなるでしょう。
このような柔軟な働き方は、利用者のライフスタイルに即した支援を実現し、働くことに対するモチベーションを高める要素となるでしょう。
さらに、フレキシブルな勤務形態を採用することで、利用者は自身の体調や生活リズムに応じて働きやすくなります。
これにより、精神的な負担が軽減され、自分に適したペースで働くことが可能になります。
生産活動の収益を増やす
内職や低単価の作業に依存することなく、動画編集やパソコン業務といった高単価な業務へと転換することが不可欠です。
このような業務は、より専門的なスキルを必要とするため、結果的に収益性を大きく向上させます。
さらに、自社やグループ会社で新たな事業に積極的に参入することは、収益を増やすための中心的な戦略となります。
こうした取り組みは、就労継続支援A型事業所の存続においてとくに重要であり、経営基盤を強固にする要素といえるでしょう。
収益の向上は、単なる数字の増加にとどまらず、事業所全体の運営に良い影響を与えます。安定した収益が確保されることで、利用者に対してより充実した支援を提供できる環境が整備されます。
結果として、利用者にとっても働くことへのモチベーションが高まり、より質の高い成果につながる可能性が高まるでしょう。
このように、収益を増やすための活動は就労継続支援A型事業所の生命線として最も重要なポイントです。
利用者のスキルアップ機会を作る
利用者の知識や能力を向上させるための支援については、行政が認めるものでなければスコアに算定されないため、ハローワークが実施する就労準備訓練や、身だしなみ、ビジネスマナーに関する教育などをおこなうことが必要です。
これらのプログラムを通じて、利用者は職場で求められる基本的なスキルを身につけることができます。
また、適切な支援を提供することによって、利用者が自信を持ち、社会で活躍できるための準備を整えられることが期待できます。
経営難による閉鎖リスクを回避するための就労継続支援A型対策一覧
2023年3月末時点で、厚生労働省が就労継続支援A型の生産活動を調査した結果、生産活動の収益が利用者の賃金総額を下回っている事業所は、3,715社のうち1,882社でした。
約半数の事業所が赤字のなかで利用者を雇用しているため、今後も経営難による事業所の閉鎖リスクは増加すると推測されます。
ここでは、就労継続支援A型事業所の閉鎖リスクを回避するために、事業所ができることについて解説します。
新規事業の立ち上げ
事業所が経営難に陥らないための対策として、顧客基盤の拡大があります。
既存顧客との取引を持続させることはもちろん、新規顧客との取引口を増やしていけば収益の拡大・安定につながるからです。
現状、インターネットの普及に伴い、新規顧客の開拓は競争率が激化しています。
そのため、地域という共通点を活かして地元の企業と連携を強めたり、他社との差別化を図るためのマーケティングを見直して異なるアプローチをしたりしましょう。
スタッフのケア
就労継続支援A型事業所のスタッフには、仕事の指示や管理、サポートをおこなう役割とともに、福祉事業所の職員として障がいや病気に対して適切な支援を提供することが求められています。
そのため、仕事のスキルを向上させることやスキルを学びなおすことはもちろん、福祉に関する専門性を高めるための研修が必要とされます。
また、スタッフ自身のメンタルケアやストレスマネジメントも重要な要素です。
こうした取り組みを通じて、スタッフが自己管理を適切におこない、より良い支援を提供できる環境を整えていきましょう。
一般就労を目指した施設運営
補助金や助成金を目当てに事業をおこなっている状態では、利用者が賃金以上の事業収益を生み出すことがむずかしいため、基本報酬の減収による経営難につながりやすいです。
既存顧客や地域との連携を深める作業に注力したり、新規顧客の開拓をしたりして、多角的に収益を出せるように運営方針を見直してみてください。
また、利用者がより高単価な業務をこなせるようなステップアップや労働環境の整備も必要です。
安定した収益が出せる事業所であれば、より環境整備の選択肢が増え、結果的に利用者の定着につながります。
ここ最近の業界状況と就労継続支援A型が直面する課題を総合的に検証

経営者と企業視点、利用者の声、2024年問題、経営難による閉鎖リスクなど複数の側面から就労継続支援A型が直面している課題を想定しました。
事業所の閉鎖が増加している主な要因は、生産活動が赤字になるとマイナスの評価がつくようになった2024年の報酬改正といえます。
内職や低単価の作業に依存している利用者を抱えていて、賃金以上の事業収益を生み出せずにいる事業所は、基本報酬が減収されるので経営難に陥っているのが現状です。
今後の就労継続支援A型は、高単価の業務にシフトしていく必要があり、動画編集やパソコン業務などの専門スキルを持つ仕事に焦点を当て、収益性の向上を図ることが求められています。
また、自社やグループ会社との新たな事業への参入も、安定した経営に向けた重要な戦略となるでしょう。
さらに、利用者の知識や能力向上の支援においても、行政が認める基準が求められるため、就労に関連する訓練やビジネスマナーの教育は必要です。
ハローワークが提供する就労準備訓練などを通じて、利用者が職場で必要とされるスキルを身につけられる機会を増やすことが、今後の課題として挙げられます。
就労継続支援A型のスタッフは、仕事の指示や管理に加え、福祉事業所として障がいや病気に対する適切な支援を提供する役割を担っています。
そのため、スタッフのケアとして、スキルアップやリスキリングはもちろん、福祉的専門性に関する研修、メンタルケア、ストレスマネジメントが重要です。
これにより、スタッフが自分自身を適切に管理し、利用者に対して質の高い支援を提供できる環境を整えらることが期待できます。
このように、最近の業界状況と就労継続支援A型が直面する課題を総合的に検証することは、持続可能な運営のために必要な視点となるでしょう。
今後、柔軟で多様な働き方を取り入れること、そして地域との連携を深めることが、就労継続支援A型事業所の未来を切り開くポイントになります。
まとめ
就労継続支援A型事業所は、事業所の閉鎖や利用者の解雇が増加しており、背景には行政の方針転換が影響しています。
しかし、事業所自体でも新規事業への参入やリスキリングの取り組みなどを進め、多様な業務をおこなえる環境を構築することが求められています。
また、質の高い支援をとおして、一般就労につながる支援をおこなうことで、経営の安定化を目指すことが重要です。
当協会では、福祉事業のオーナー様向けに各種勉強会やお役立ち情報を発信しています。
協会員様になられた方には当協会が主催する「オンライン講座」に無料で参加&視聴できます。













